- #開発現場コーチング
株式会社オズビジョン

お客様インタビュー 株式会社オズビジョンCEO 鈴木良様 第2回
エンジニアのあるべき姿を本気で見せる、現場コーチがもたらした社内の劇的な変化。
2007年にポイントメディア事業からスタートした株式会社オズビジョン様。経営、企画、エンジニアなどのコミュニケーションに壁を感じていました。そこでギルドワークスの現場コーチが入ったところ、何がどう変わったのか。CEO鈴木様にお話をうかがいました。
※第1回目はこちら
経営サイドからも、現場のエンジニアからも信頼していただき、多くの成果を上げた現場コーチ中村。
しかし彼は「もうこの現場に呼ばれたくない」と言います。はたしてその真意は?
スタイル、ポリシーが劇的に変わった
鈴木様(以下敬称略):ギルドワークスさんが入る前は、経営者として開発チームにもどかしい気持ちがずっとあった。エンジニアにもユーザーのことをもっと見て、スピードを持ってどんどん改善や開発をしてほしいという思いはあった。けれど、そのまま言っても伝わらないし、自分が開発の文脈が分からないのでどこまで言っていいか分からないといった変な遠慮もあって「開発チームが言うならそうなのかな」と引き下がるしかなかった。
しかし、この2年半でエンジニアが劇的に変わりました。かつては「ユーザー視点ではこうだよね」「成果から見たらこうだよね」という話をしても「いや僕らエンジニアなんで、言われた通り作るのが仕事です」と、会話にかなり段階を踏まなければいけなかった。それが今は「ユーザーストーリーなんだっけ」「それ誰のためだっけ?何が嬉しいんだろ?」とエンジニアが勝手に話している。
中村:問いの質が変わったと言えるかもしれません。「何をしたらいいんですか」という誰かが知っている正解を探す問いから、「なぜそれを作るのか」「誰がそれで嬉しいか」という正解がない前提で少しでも良さそうなところを探索するような問いに変わりましたね。
鈴木:本当に変わりましたよ。やっぱり姿勢じゃないですかね。
中村:開発チームには、利用者から見た当たり前のクオリティの話や、何がかっこよくて何がかっこ悪いのかを何度も伝えましたし、自分達で話し合ったりもしていました。「それが月に数十万ももらってるプロの行いとして正しいと思う?」と言い残したこともありました(笑)
鈴木:技術的なことももちろんですが、それ以上に、言動の全ての源泉となる、開発という仕事に対するスタイル、ポリシーが変わった感じがします。
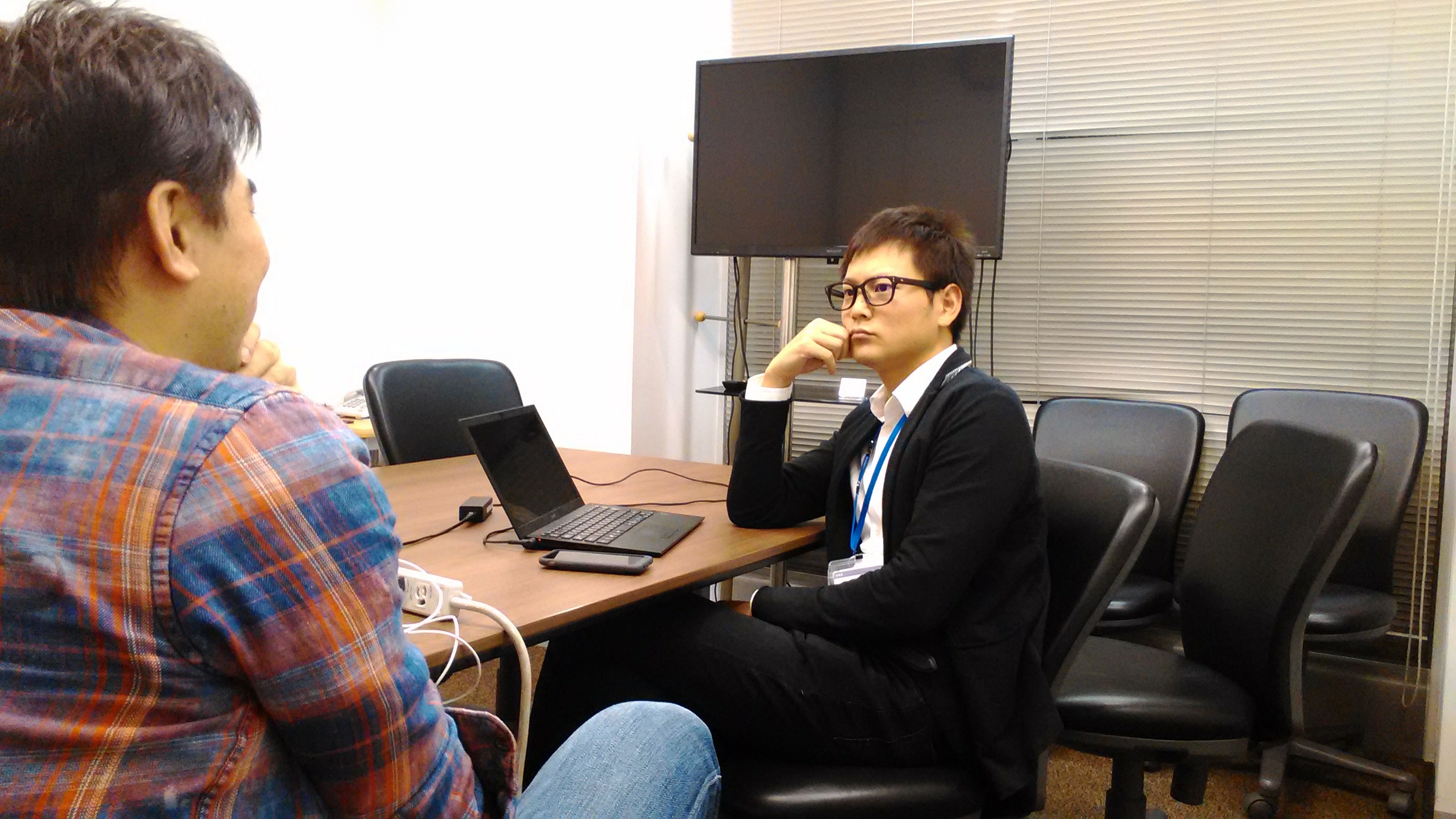
相対的な正しさ
-反発はなかったのですか?
鈴木:入ってもらって間もない頃は初めからいきなり「あるべき姿」をバシーンとやったので、中途社員からの反発がありました。新卒の子達はいろいろ学ぼうとするんですが、その上の中途社員が「あの人いつまでいるんですか」とか喫煙場でグチってたんです。愚痴の内容を聞いてダサいと思いましたね。
中村:そうだったんですね(苦笑)。話は変わりますが、悔やむことがあるとしたら、何人かエンジニア達が辞めたことに対して、本当にコーチとして何かできなかったのか?ということです。
当時はそれぞれの価値観をすり合わせることよりも、オズビジョンさん、鈴木さんの思う価値観を定着させることにフォーカスを置いたので、合わない人が息苦しくなったのかなと悩んだりしました。鈴木さんは「バスに乗れないなら仕方がない」と言ってくれたんですが、1人のエンジニアとして「自分が現場を預かるマネージャーだったら、もうちょっと早く話を聞いてあげられたら」と、やりようがあったんじゃないかなと。
鈴木:「正しいものを正しくつくる」の、正しいっていう概念に「万人向けの正しさ」はないじゃないですか。正しさは相対的なもので、正しくないことがあるから正しいことがあると考えています。全員にとって正しいわけではない。ただある方向の正しさに振り切るということは、正しいとそうでないものを区別するのであって、どうしても合わない人も出てくる。でもその人が悪いわけではない。
「あれもそれもこれも正しい」と中途半端にやるよりは「うちにとって正しいのはこれです」と示して、自分の価値観とは違ったと早く気づいてもらう。そのことはその人の人生にとってプラスになる。だからその人が辞めたことは逆に良かったのかなと思います。
中村:鈴木さんのおっしゃる「相対的な『正しさ』がたまたま自分の価値観とは違っていただけ」と伝わっているといいと思います。
劇的な変化
中村:現場がだいぶ頑張ってくれて、最初の一年間でプロダクトのリリース数が2倍、リリースするまでのリードタイムも1/2になったりと、具体的な数字の面で改善されていったのはよかったです。経営者の鈴木さんが「現場の空気が良くなったね」と言ってくれても、成果として見える化しておきたかった。どのくらい早くなっているとかどのくらい不具合数があがって、これがこうなっていってまたこういう問題は上がっている、とつねにレポートを出していました。
鈴木:中間もいろいろありましたが、すごく劇的な変化ですね。
中村:ここで社外勉強会もしましたよね。
鈴木:中村さん達が来てくれたから、勉強会をうちが初めて主催した。
中村:最初は社外勉強会のやりかたもわからなくて、やりたいねで止まっていました。そこで、じゃあ手伝うよということで、同業他社のエンジニアを中心に声をかけてもらって30人ぐらいでやりました。今では、若手の何人かは、外の勉強会で発表したりする人もいるみたいです。
鈴木:いろいろなテーマで合宿もしましたね。開発チームの合宿もしましたし、開発の現場コーチという枠を飛び越えて事業戦略の合宿を2回ぐらいやりましたね。
中村:一緒に一泊二日のアジェンダを作って、こちらが投げるタフクエスチョンに一生懸命考えて少しずつ前に進むという感じでしたね。
開発チームの合宿で印象に残っているのは、テストコードを書く合宿。当時はユニットテストを日常で時間をしっかりとって書けなかった。そこで、金曜日の午後から、私ともう一人のコーチと若手メンバー4、5人で2泊3日で行ったんです。合宿では、昼間はコードを書いたり、それにまつわるディスカッションをしたり勉強して、夜は喋って遊んで。
印象的だったことは、その合宿の準備の時に「お金どうするの?」と聞いたら、彼らは「自分たちで出す」と言ったことです。それだけ本気だったらと私も思いました。途中から「しんどいし、色々課題もあってすぐ出来ないけど、なんとかうまくなりたい」って雰囲気が本当にでかくなっていきました。それがすごく良かったです。

-それは応えたくなりますね
中村:鈴木さんの信頼もそうですが、現場の信頼を裏切りたくない気持ちは、すごくありました。当時の現場には背中を追う存在がいなかった。そんな中、自分たちギルドワークスがしょうもないことをやると「こんなんでいいんだ」というメッセージを送ることになる。特に最初の頃は、ある種の正しいエンジニア像のロールモデルを見せることを意識しました。後半は「自分達でより考える」という方向に振り切り「これも一つの形やし、自分らの形を見つけてみて」と言っていました。
-段階を追って接し方を変えていくという戦略?
中村:結果的に変わっていたという感じですかね。最初は教えることが多かったですが、途中から、しんどくても自分達で考えていくことをやりたいと考えていたので、彼らには「自分で考えて、成長してもらう」という方に接し方を変えましたね。
「この人たち本物だ、マジで信頼できる」
-ところで、今だから語れるエピソードってありますか?
中村:代表の市谷と私が鈴木さん達の前でケンカしたことがありましたね。
鈴木:ありましたね。ある時、サーバーのトラブルでうちのサービスが何回も止まったり不安定だった時期がありました。その対策を考える席で、中村さんは「この時間軸、順番でこういうふうに行くのがいいと思う」という、でも市谷さんは「そういう問題ではない今すぐやるんだ」というようなことを2人で言い合いになり始めました。
中村:私はコーチの立場から「この段階だったら、チームに育っていって欲しい点も踏まえて、こういう時間軸でやった方がいい」という話を、彼はサービス開発の視点で「そんなもんどうでもいいからすぐやるんだ」という話を。オズビジョンの社員さんは普通にしているのになぜか他社の人同士で言い合いのケンカをしているという風景でした(笑)
鈴木:最終的に市谷さんがプルプル震えながら「だったらいつハピタスのサーバーは安定するんだ!」と怒るのを聞いて「この人達本物だ、マジで信頼できる」と思ったんです。取引先の会社ですから、普通、中村さんと市谷さんの2人で「ちょっと」と話をして戻って「こうしよう」という感じですよね。それをその場でやりあう、つまり常日頃からそのくらいの温度感でサービス開発に向き合っているんですね。「正しいものを正しくつくる」という理念に対して本気じゃないと、あの場であの瞬間に、ああいうセリフは出てこないですよ。
いなくなってからがコーチの価値
鈴木:2年半の中で、現場コーチ、CTO代行を止めようと思ったことはありますか?
中村:何度かありますよ。マンネリ感があり、あまり発展性がない時期がありました。週2日、企画チームや開発チームを見てフィードバックをして、時々は鈴木さんと経営の話をして終わりみたいな。やっていることは大きく変わらないのですが、どこか惰性でやっている感があり、よくないなと思いました。課題は解決していたし、バリューは出させていたと思いますが、最初のような劇的というほどでなく、タフクエスチョンが飛んでいるわけでもなく。その時期は「これやっていて嬉しいのかな?本当にためになっているのかな?」と思ったりしていました。
その頃、ありがたいことに第2、第3の現場コーチ先が本格的に動き始めていて、そこに集中したいという背景もありました。そんな新しいクライアントになかなかパワーを振れない。自分の関わる時間を減らすか?など考えていました。ただ、ありがたいことに中村個人のことも信頼いただいていたようだったので、ギルドワークスの他の人がコーチとして代わりに来るのはあまり現実的ではないなと思っていました。抜けて誰かを代わりに入れる、というのではなく、現場コーチとしては一旦終わりましょう、という選択はしたと思います。
鈴木:多分同じタイミングで私も同じ事を感じていて、逆に現場は「もっと来てほしい」というのがあって、そこに危機感を覚え始めたんです。いつまでたっても中村さん離れができないのは困る。前から中村さんは「自分がいなくなった後にその現場が成長し続けるかどうかがコーチの成果だ」と言っていましたね。
最終的にどうなったかと言うと、冒頭でお話したように今はお願いしてないんです。どうしてお願いしていないかと言うと「一旦自分達で自立してやってみたい」と現場で決めたことがきっかけだったんですよ。2年半経って最初の頃に宣言した「コーチのあるべき姿」にまでいっていて、本当に劇的に変わりました。今、「自分たちでやっていく」と言った若手達は自立してやっています。

中村:ふらっとやってきてお茶しながらディスカッションしたり、勉強会とかでしゃべったり「たまに来るおっちゃん」だといいのですが、「またちょっと大変になったから来て」と言われるのはイヤだなぁと思っていますよ(笑)。
鈴木:また戻ってきたら、後退、退化した感じありますよね。もう一回やり直しかい、みたいな。
中村:自分もできればそういう声のかけられ方で呼ばれたくないですし。彼らならがんばってくれると思いますし、できると思ってます。
改善は常に前へ進む、変化していることが大事で、前と同じ事をやっていることも、「なんでやっているの?」と問われて「3ヶ月前からずっとこうだからです」と理由がいまいちなのも良くない兆候だと思っています。新しいことをやっていたり、止めたことも「こういうことがムダになったので止めました」とあれば良くて、その点でたぶん彼らは大丈夫なんじゃないかなと思います。
「いなくなってからがコーチの価値」という中村の言葉は、オズビジョン様の開発チームではどう受け止められたのでしょうか。
次回は現在、開発チームの一員として中村のDNAを引きつぐ、若きスクラムマスターたちにヒアリングします。
こんなことでお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。ギルドワークスのメンバーがお話をお聞きします。
- 立ちあげたい事業があるが、本当に価値があるのかどうか自分で確信が持てない
- 新規事業を立ち上げなければならなくなったが、潤沢な予算があるわけでもないのでどうしたらよいのかわからない
- 企画が実現可能かどうか開発の視点を組み入れながら仮説検証したい
- はじめてのことばかりで右も左もわからない
