- #開発現場コーチング
株式会社ヌーラボ

お客様インタビュー:株式会社ヌーラボ 中村様・縣様(後半)
現場コーチ中村とディスカッションを重ねたことで、チームへの接し方が変わったという株式会社ヌーラボの中村知成様。その変化はどのように波及していったのでしょうか。今回はヌーラボの創設者の一人でプロダクトマネージャーの縣様にも加わっていただき、お話をうかがいました。
(肩書き、状況などは2017年2月8日当時のものです)
※前半はこちら
上司から見てリーダーはどう変わったか
-上司から見て知成さんの大きな変化はありましたか?
縣様(以下敬称略):僕からすると、前と後では全然違って見える。フワっとしたイメージですけど「変わったな」って気はします。
僕が知成さんに「ちょっと期限切ってスクラムみたいな感じでやってみようよ」っていった時、けっこう勇気が必要だったんですね。彼はスクラムとかアジャイルみたいなプロセスに興味を持っているようには見えなかったし、チームも「やりたい」って感じでもなかったんで、ドキドキしながら始めて。
それがすごい勢いで学習して、スクラムとかアジャイルとかの伝道師みたいになってくれた。正直嬉しい誤算でしたね。逆になんでそんなにハマれたのか僕が聞きたいくらいです。
中村(知)様(以下敬称略):当時は前任のリーダーがニューヨークに行って僕が引き継いだ時で、自分の作業以外にも、他の人の相談を数多く受けたりして僕がボトルネックになって辛かった。
それまでは前のリーダーと僕とである程度分担できていたのが、僕一人の負担になって「これは立ち位置自体変えないと多分無理だな」と思っていた状況でした。
縣:人が増え始めた頃にリーダーが中村(知)さんに変わって、やらなきゃいけないことがだんだん積み上がるけど、新しいこともやりたいし、っていうタイミングだった。
-変化に対して、反発とか抵抗はなかったですか?
縣:Backlogチームに関しては大丈夫でしたね。今後この動きを会社全体にも広げたいのですが、そこは未知数です。すぐみんなが真似しないところを見ると、少し抵抗感はあるかなって感じはしますね。ただ、そういうところもBacklogチームが成果をどんどん出していけば変わっていくとは思います。
中村(知):大きい抵抗がなかった一因として、僕や縣さんがある程度決めることができる立場というのがあると思っています。もしかしたら「ちょっと変えるのやだな」と思っていた人はいたかもしれない。でもトップがやろうっていったら、ある程度は乗ると思うので、その点はやりやすかったかなと思っていますね。
縣:素養のある人がいたというのも大きかったですね。洋さんと以前一緒に働いていたメンバーもいたし、それなりに効率的なモノづくりが好きな人が多いので「効果があるならやろうよ」という感じはあったと思います。
中村(洋):プロダクト自体がコラボレートをテーマにしているので「チームでこうしたらもっと良くなりそう」ということにはやってみようという感じは強かった気がします。やってみてやめた施策もあるでしょうし、そこは選択できるようにやり方や道具を背景と共にお渡しして、自分たちで試してもらって、良かったら続けてみましょうというパターンがわりと上手くいったと思います。

インセプションデッキで思いをひとつにする
-現場コーチの伝えたノウハウがBacklogのプロダクトに反映されたというのはありますか?
縣:今やっている大きめのプロジェクトではインセプションデッキ(※)がアウトプットに影響してくると思います。やらなくてもできたかもしれないけど、プロジェクトの方向性がメンバーでバラバラになる確率はかなり下がったんじゃないか、まだ影響は出てないけどいい効果を与えたものが今進んでるって思ってます。
※インセプションデッキ
アジャイル開発で使うプロジェクトの計画書。プロジェクトの方向性がぶれないよう共有するためのもの。みんなで議論して決め、アップデートすることに特徴がある。
中村(洋):人数が少ない頃は「それはどんなプロダクトになるの?」が以心伝心で伝わった環境だったと思います。でも人が増えてその以心伝心さが薄まってきたり、やりきれなくなってきた。そうなるとプロジェクトの後半で「え?その方向に走ってたの?」って言う人が出てきてプロジェクトが残念な結果になる。
そうならないように「このプロジェクトはどこに向かって走るの?どうやって、どれくらいの早さで走るの?」といったことをチームで話し合って共通認識を作る必要があります。その道具の1つとしてインセプションデッキを紹介してやってみたところ、「僕はそうは思っていなかった」という違いが表面化したり、そういうことへの議論や理解が深まって「じゃあこの方向だったら走れるね」ってなりました。そこから作り始めるので、やっぱりずれは少なくなる。
縣:そのプロジェクトに僕はもうほとんど関わってないんですが、以前だったら、やっている人たちもモヤモヤしてたと思うし、僕自身も不安で耐えきれず細かくチェックしたり、レビューに入りたくなっただろうと思います。今はすごくクリアになってきて、二週間に一回のふりかえりなどに参加すればなんとかなる。すごい安心感がありますね。
中村(知):半年以上の期間のプロジェクトだと「どう作ろうか」っていうのが、フワフワして見えづらかったんですが、今は「ここをこう作ろう」「このためにこう作ろう」っていうのが縣さんの立場からもやってる人からも関係者全員から同じものが見えている。
中村(洋):印象深かったのがインセプションデッキを使って議論しているとき、縣さんがみんなに「こうやるんや」って喋るんではなく、みんなが同じ目線で「僕はこの方向を目指したほうがいいと思う」とか「納期と機能だったらどちらの方を優先すべきか?」とかフラットに議論していたんですよ。作るものであるWhatだけを伝えてたら「その進捗大丈夫?」となるんですが、このチームでは「なんでそれをやるのか?」というWhyの議論が多く出ていてて、私はあまり踏み込まなくても大丈夫だなと感じました。
問いがあればいいというわけではない
-それを聞いてインセプションデッキがあれば、現場コーチがいなくてもできるんじゃないかという気がしてしまったんですが?
中村(洋):もちろん自分達だけでできる場合もあります。ですが、最初は、自分達が答えにくいタフな質問を十分にできず、表面的な会話だけしてしまうこともあります。
中村(知):「これはみんながより便利に使えるプロダクトです」では結局何を言ってるのかよくわからない。「みんなって誰よ?」「より便利って具体的にどう便利になるの?」みたいな話をして行く感じですね。
中村(洋):そうですね。また、個別の質問に答えた内容を繋いでみると真逆のことをいってるとか整合性が取れていないとかがでてきます。そういうのは外からのほうが見えますし、ある意味遠慮なく言えます。「この質問と次の質問と答えがちゃうねんけど。なんで?」って問いかけると「あ…」って。
中村(知):そういう認識のずれを合わせないままだと、いざ問題に遭遇した時に判断がバラバラになる。その辺の意識を合わせて行く感じですね。
中村(洋):なぜ「この問いなのか」を知ってる知成さんのような方がいたら大丈夫ですが、逆に知成さんがブロジェクトメンバーだったらやっぱりそこが辛くなるんですよね。「なんか言うとめんどくさいし、俺もちょっと巻き込まれるし」って、当事者になるとなかなか言いづらくなるんで。
中村(知):自分が一員になると言いづらくなるのはありますね。やっぱり外からだと見えるものがある。
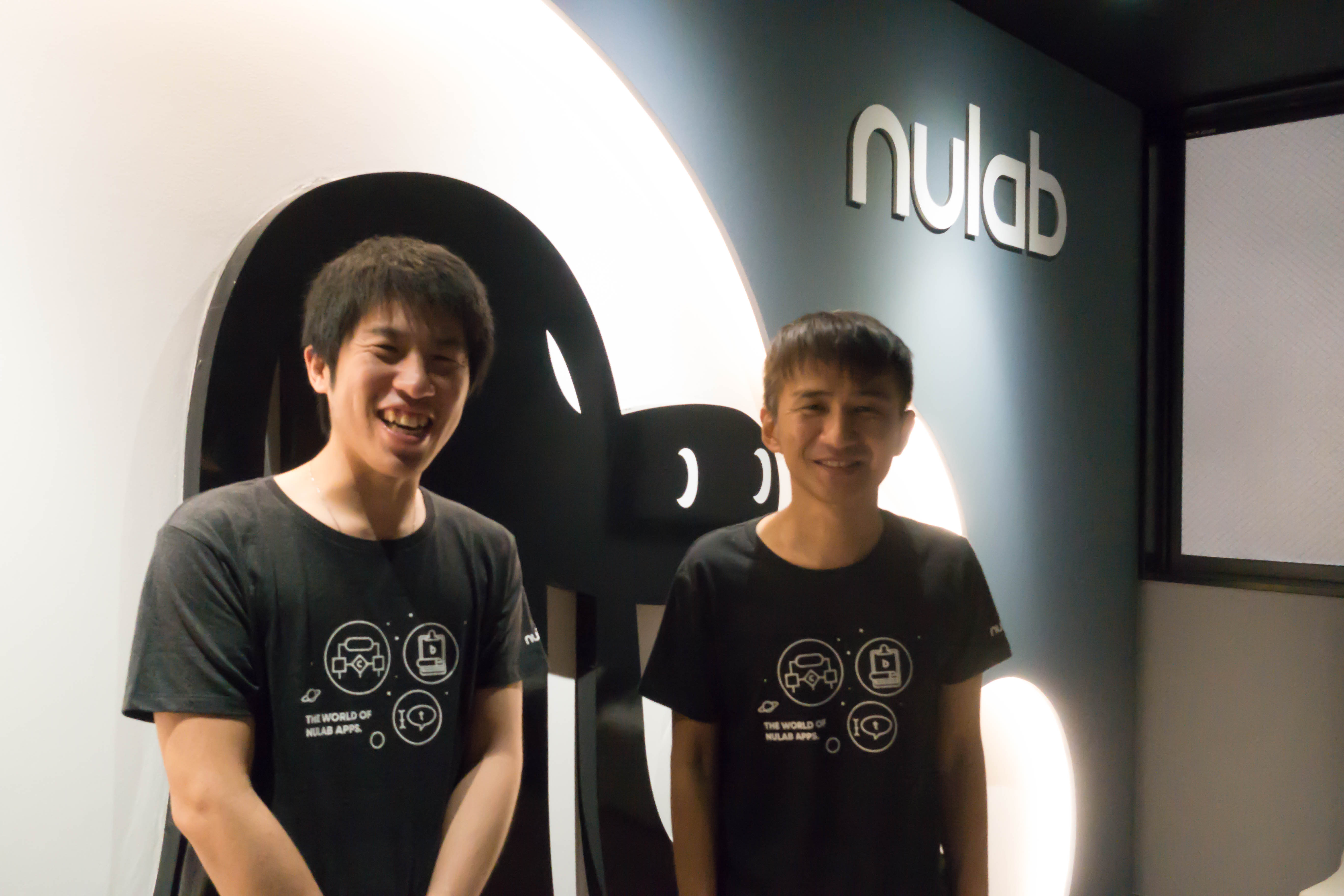
今後は他のチームに横展開をしていく
-今後は、他のチームにも現場コーチを入れてって感じでしょうか?
中村(知):まだまだなところはありますが、Backlogチームはできるようになってきた。せっかくなんでCacooやTypetalkといった他のチームとか会社全体に広めていきたいと思っています。
縣:僕も同じような気持ちですね。
中村(洋):将来的に、知成さんがBacklog以外の2つのプロダクトに関わる中でまた違う壁にぶつかるかもしれません。文化が違うでしょうし「うちらのやり方がある」となるでしょうし。そういう時に「こんなんぶつかってんけど、どないやろ?」みたいな疑問に「どう思う?こんなんやったらええんちゃう?」と問いかける、というように知成さんを通じてサポートできればいいかなと。
中村(知):今の所は僕がそういう形で動けると会社的にも嬉しいのかなって思いますね。いつまでも外部の方に頼ってると僕らの成長がなくなるんで。
中村(洋):知成さんに「なんで?」って聞くようにしていたのは、その道具がなぜ存在しているのか、どんな時に効くのか、ちゃんと伝えるためです。もちろん知成さんに受けとめてもらえる前提で話しているんですが。
-応用が利くように、ということですか?
中村(洋):インセプションデッキも「ベーシックはこうだけど、こういう場合にはこうしたほうがいいんじゃないかな」とか私なりの経験や考えを伝えています。
他の現場では出てこない質問も彼からあるんで、私自身も勉強になる。その道具がなぜそうなってるのかとか、なぜ私があそこであんな発言をしたのか、あるいは、なぜ言わなかったのか。普通の現場からはそんな質問はあまり来ないので、そういうのは楽しいですね。「そこ気にすんねや」とか思ったり。
中村(知):「なぜ言わなかったか」を聞くことは多いですね。例えばあるミーティングの前に二人で「こういうことを話しましょうか」と作戦を考えていても、実際に洋さんが言わないこともあります。そうするとやっぱり気になるんで後で聞きますね。
中村(洋):一例ですが、いい会話をしてたから場の流れを止めないようにしたとか。
知成さんは言おうって思ったことはその通りにいうタイプなので「なんで決めたこと言わなかったんですか?」「いや、こういう流れだったからですよ」って話をして。そういう質問に対して自分なりに考えるのは自分も勉強になったし、面白い組み合わせだなと思っています。
縣:一年を通してだんだん余裕というか柔軟性が出てきましたね。前は教科書通りっていうか、型から外れるのは認めないみたいなところがありました。今は目的が達せられるなら柔軟にアレンジしてもいいじゃないですかという感じで。その辺実際に参加していた人たちも硬さが取れた感じじゃないかな。すごく上手になったんじゃないかなって思います。
中村(知):教科書を外れるとうまくいかないことが多いって今でも思ってるんですよ。でも「だから教科書通りにやろう」では、みんなはなかなか感情的にもついてこれない。腹落ち感がないまま進んでもうまくいかないというのも実感できました。なので、多少教科書を外れても、やりたいようにやってもらって、うまくいかなかった場合は振り返りの時に「なんでうまくいかなかったんだろう?」と話す、という方向に持っていこうとしています。カスタマイズ、アレンジして問題がなければ、それはそれで全然問題ないので。
縣:少し長い目で見られるようになったんですね。
-すごく頼れるリーダーですね。
中村(知):そう思ってもらえると嬉しいですね。
自分の枠を越えてリーダーとしてさらなる成長をとげた中村知成さん。今後の活躍が楽しみです。
こんなことでお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。ギルドワークスのメンバーがお話をお聞きします。
- 立ちあげたい事業があるが、本当に価値があるのかどうか自分で確信が持てない
- 新規事業を立ち上げなければならなくなったが、潤沢な予算があるわけでもないのでどうしたらよいのかわからない
- 企画が実現可能かどうか開発の視点を組み入れながら仮説検証したい
- はじめてのことばかりで右も左もわからない
