- #開発現場コーチング
株式会社オプト
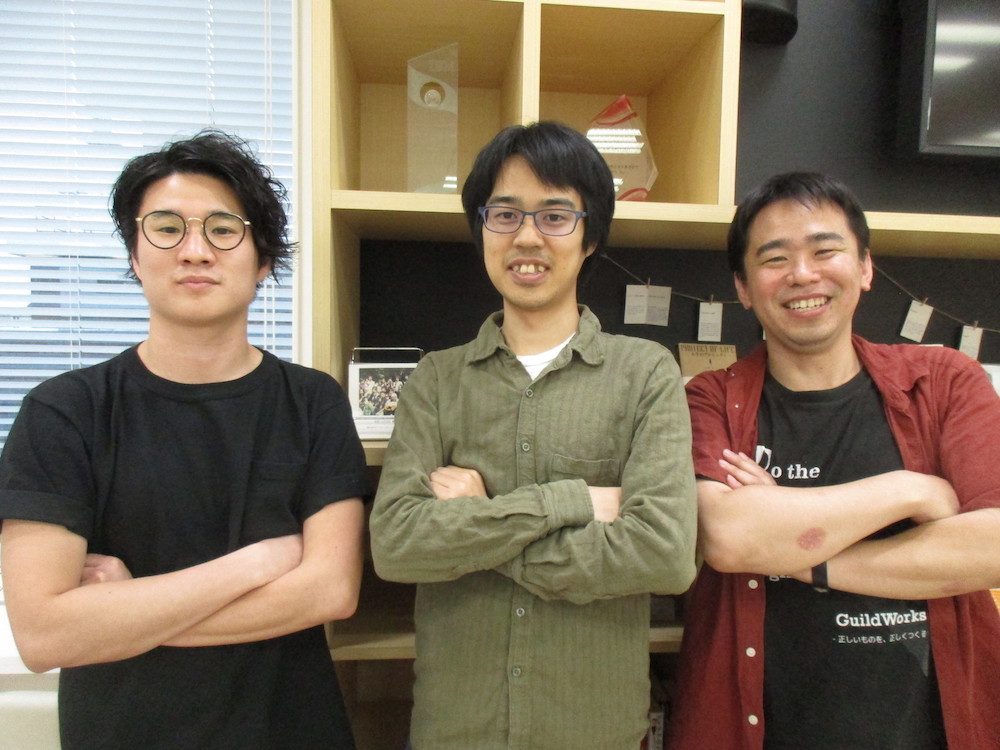
お客さまインタビュー:株式会社オプト 虎谷様・伏見様
現場コーチがもたらした「なぜやっているのか?」「どうなったら嬉しいのか?」問い。それがチーム全体の視座を上げるきっかけだった。
累計1,500社の導入実績を誇る広告効果測定ツールADPLAN(アドプラン)を提供しているインターネット広告代理店オプト様。今回は現場コーチ中村がADPLANの開発チームにもたらした効果について、ADPLANの開発チームの虎谷謙太様と伏見大輔様にお話をうかがいました。
(肩書き、状況などは2018年6月6日当時のものです)
手探りのスクラムでは限界があった
中村:ADPLANの開発チームのうち虎谷さんは新機能を追加していくチームのプロダクトオーナー、伏見さんはコストを下げたり安定性を支えたりするチームのスクラムマスターです。最初にうかがったのは2017年8月ですね。しばらく隔週で通って、2018年1月から5月はほぼ毎週。今(2018年6月)はそろそろ落ち着いて隔週になってきた感じですね。
伏見様(以下敬称略):中村さんに依頼することになったのは、2016年10月に当社で始めたスクラムで解消できない問題があったからです。スクラム以前は、何を開発しているのか見えにくい、いつリリースされるのかわかりにくいなど、開発側がビジネス側の要請に対して答えられていない状態でした。また、指揮統制型というか、一部の人しか全体の開発の方向性を考えられず、チームになりにくい状況でした。
そこでスクラムを取り入れれば問題を解消できるだろうとはじめたのですが、解消しませんでした。そこでプロに手伝ってもらいたいというのが中村さんに依頼した背景です。
虎谷様(以下敬称略):それまでも本を読んだりして、手探りで進めていました。手探りなりにいい線は行っていたと思うのですが「やはりプロに指導を仰ごう!」という感じでしたね。
「なぜ」という問いを立てて変わったこと
--初対面の印象はいかがでしたか?
虎谷:僕はファーストインプレッションで「結構すんなりいけるな」という感触を持ちました。中村さんも僕も地元が大阪だからかもしれません(笑)。
伏見:2017年4月に自分がスクラムマスターになった時に、まずはスクラムの「守」をやっていきましょうと動いていたところで、洋さんが手伝いに来てくれた感じです。
最初は洋さんから溢れてくる情報量があまりにもすごすぎて、「あー!受けとめきれない!」って感じでした(笑)。洋さんの言葉すべてが自分にとっては新しさに溢れていて「この人は組織の改善にかなり力を与えてくれそうだ」と思いました。実際、洋さんの後押しがあって、チームとしての協業が進んだと思っています。
中村:すでにある程度スクラムをやっているとうかがっていましたので、最初は観察モードで入りました。
最初はプランニングやふりかえりなどのスクラムイベントを見て、観察したことや思ったことをフィードバックしましす。観察した中で大きく感じたことは、みんなが納得してやっているように見えなかったことです。色々な人に「これはなんでやっているのですか?」と聞くと、「前の人がやっていたから」「教科書に載っていたから」という答えでした。自分で考える癖がついていない様子でした。
伏見:当時の僕らには洋さんの視点というか切り口が新鮮でした。「なぜそれをするのか?」と明確な質問で、自分たちが意識しなかった視点を与えてくれるので「あ、確かに!」と気づけた。
--具体的にはどんなことがありましたか?
伏見:作る機能の話をする場で「Excelダウンロードで提供していたデータをCSVにしたらパフォーマンスが改善するんじゃないか?」という話になったことがありました。
中村:そこで「どれぐらい早くしたいと思っているんですか?」「お客さんに聞いたのですか?」「それは、どうなれば解決なのですか?」と聞いても誰も答えられなかったんです。
虎谷:僕も答えを持っていなかった。明確に答えなければいけない立場だったのに「なぜ?」がなかったですね。
伏見:お客さんが何に困っていてどうなれば解決なのか、なぜこれを欲しているのか、開発者も、プロダクトオーナーも、全然意識していなかった、ということがわかりました。
中村:「なぜ作るのか?」という問いを立てず「言われたから作るんです」という感じでした。
--問いを立てることに対して、メンバーから抵抗はありませんでしたか?
伏見:なかったですね。「なるほど!洋さんすごいこと言っているぞ!よしやっていこう!」って感じになったと思います。
虎谷:チームとしては前向きでしたよね。「もっと良くなるんだ」みたいな。
伏見:もともと「なぜ作ってるんだろう?」と感じていた人もいたと思います。疑問というか「この機能がどう使われるのかわからないけれど、言われたから作るか」みたいな。
--問いを立てることによってチームは変わりましたか?
中村:多分、チームのメンバーと虎谷さんとの会話の質が変わっただろうと思います。「次、どんな機能を作ろうか?」という場合、以前は、虎谷さんの「こういうものを作りたい」に対して、メンバーの「じゃあ仕様はどうしますか?」「仕様を決めてください」という会話だったと思います。今は「それをどうやってユーザーは使うんですか?」「こうなったらもっとユーザーは喜ぶんじゃないですか?」とアイディアが出るようになったと観察していて感じました。
伏見:そうですね。「なぜ?」という問いをメンバーがするようになりました。虎谷さんが「こういう仕様のものを作りたいです」と伝える時にも、「なぜ?」があることが当たり前になりました。
虎谷:「なぜ必要なのか」について、以前は少ししか書かず、説明も「必要らしいから」とか「前のバージョンであったからです」とか、浅かったのです。
今は「こういう理由で必要です」という説明を厚めにしています。自分たちが作るものは、誰がどういう風に嬉しいのか、その機能を作る背景を厚めに話さないと、グッと入らないというか。
中村:何を作ればいいかだけではなくて「ユーザーはどんな機能が嬉しいの?」みたいな「嬉しさ」の方向に開発メンバーが目を向けてくれる。
虎谷:確かにチームから「これ、誰がどのくらい嬉しいんですか?」という言葉が出るようになりました。
「誰がどのくらい嬉しいか」について全員で認識をあわせて「じゃあこういう機能がいるんですね」と入っていくと細かいところも作り方が変わってるんですよ。「こういうことなら、仕様にこういうのいるんじゃないですか?」「確かに」みたいなやりとりがありますね。それをすごい良いなと思っています。
伏見:なかでもそういうことにあまり興味がないように見えた開発者のTさんが「どうなったら嬉しいですか?」という言葉を使っていたんですね。洋さんがよく言う言葉をそのまま。
虎谷:最初は「わかりました。では作ります」みたいな感じだったんですが、変わりましたね。
伏見:年齢も上ですし、静かに開発できれば良いみたいなタイプで変化が現れやすい人ではないんですね。以前は、ペアプロも絶対嫌がっていたのですが、今は自分から「モブプログラミングしましょうか」って言いだします。洋さんに影響を受けて彼が一番変わったんじゃないかなと思っています。
中村:そうなんですか。意外ですね。どちらかというと「僕はそういうのはいいので…」というような消極的な態度だったので(笑)。
課題決定できる人を増やしたい
伏見:うちは半期ごとにチームの再編が行われるなど、状況が変わりやすくチームビルディングも結構大変です。ただ、チームが変わることによってチームビルディングが大変だ、という課題感が出てきたのは最近の話で、当初はチームとして動いていなかったので、そこは課題感ではありませんでした。
中村:「集まって、いい感じにやってます」みたいな感じでしたね。
伏見:当時はチームというよりはグループでした。今は、みんながチームで、という動きをしているので、チームが短期間で変わることにネガティブな感情を持った人が増えてきています。
中村:そう言えば最初の頃、会議室で長時間、A案B案C案のメリット・デメリットを話し合っていたことがありました。何時間話してるんだろうって思いました。席に戻って30分でも各々で手を動かしたらアプローチがわかるじゃないですか。話すよりやってみれば…。
--手を動かさずに頭で考えてしまっていた、なぜそうなっていたのでしょうか?
伏見:それまでそうしてきたという文化があったからだと思います。当時はリスクはなるべくつぶして「ここまで考えたら大丈夫だろう」という案でないと通らなかった。
虎谷:あとは多分、当時は決め方がわからないというのもあったと思います。
中村:「ではこうしましょう」と決めるリーダーが抜けてからは、割とみんな手探り状態でしたね。
伏見:「自分たちで決定ができない」課題感がありました。洋さんに入ってもらったばかりの8、9月頃はそういうカラーが顕著に出ていたと思います。
最終的にはプロダクトオーナーが意志決定するのですが、開発者にゆだねられている部分も多くあります。自分たちで考えて自分たちで決められる開発者を増やしたい、自己組織化チームにしたくて、そのために自分はスクラムマスターとしてやってみたいという風に動いていました。
ユーザーテストで開発者の視座が上った
--問いかけの他にはどんなことをしていたのですか?
中村:直近のエピソードで面白かったのは、ユーザーテスト(※実際のユーザーを招き、使っているシーンを観察する)でした。それまで開発チームは、虎谷さんから「ユーザーはこうやっていたよ」と聞くことは多かったんですが、実際に使っているところを見たことがありませんでした。そこで少しお願いして、ユーザーの方にリリース前の機能を特に説明なく触ってもらったんです。
目の前で使っているのを見ると開発者の顔つきが変わりました。「そう使っているんですね」「それに気づかないのか」とか、虎谷さんも気づかなかった便利さ、不便さが新たにわかりました。ユーザーテストが終わってからみんな「こんなことで喜んでくれるなら、すぐに直しましょう!」と。
虎谷:作り手側にいると「どうせこう使うでしょ?」って先入観が入るんですよ。ユーザーテストで「なるほど、この人たちはこう使っているのか」と改めてわかりました。あれは意味がありましたね。
中村:実際に使用している様子を開発者が見て、肌で感じて「じゃあ、次こうしたらいいんじゃないですか?」となると、プロダクトオーナーも楽になってくるんですね。
私は良く「視座が上る」と言うのですが、背景を説明しなくても、ユーザーがどんなことで困るかが肌感覚でわかりますから話が早いし、そうそう方向も違わない。どんどん良い循環で回ります。それがこの2ヶ月の間にできました。
--働く姿勢、作る姿勢が全く変わってきたのですね。
虎谷:そうです。洋さんが入ってくれたタイミングがとても良かったと思っているんですよ。2018年の上期くらいまでは、旧バージョンを閉じていく機能を作っていたんですが、その間の約10ヶ月くらいかけてチームの体勢を構築できた。今は「さあ行くぞ!」となった時にドライブをかけられるチームの体制ができている。とても良いタイミングだったと思っています。
現場コーチが入り「問いを立てる」という体験を通して、漠然とした課題を解決しつつあった開発チーム。
次回は伏見様、虎谷様、個人の変化と、個人が変化することによって、組織がどう変わりつつあるのかについてお伝えします。
こんなことでお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。ギルドワークスのメンバーがお話をお聞きします。
- 立ちあげたい事業があるが、本当に価値があるのかどうか自分で確信が持てない
- 新規事業を立ち上げなければならなくなったが、潤沢な予算があるわけでもないのでどうしたらよいのかわからない
- 企画が実現可能かどうか開発の視点を組み入れながら仮説検証したい
- はじめてのことばかりで右も左もわからない
