- #顧客開発コーチ
株式会社エムティーアイ
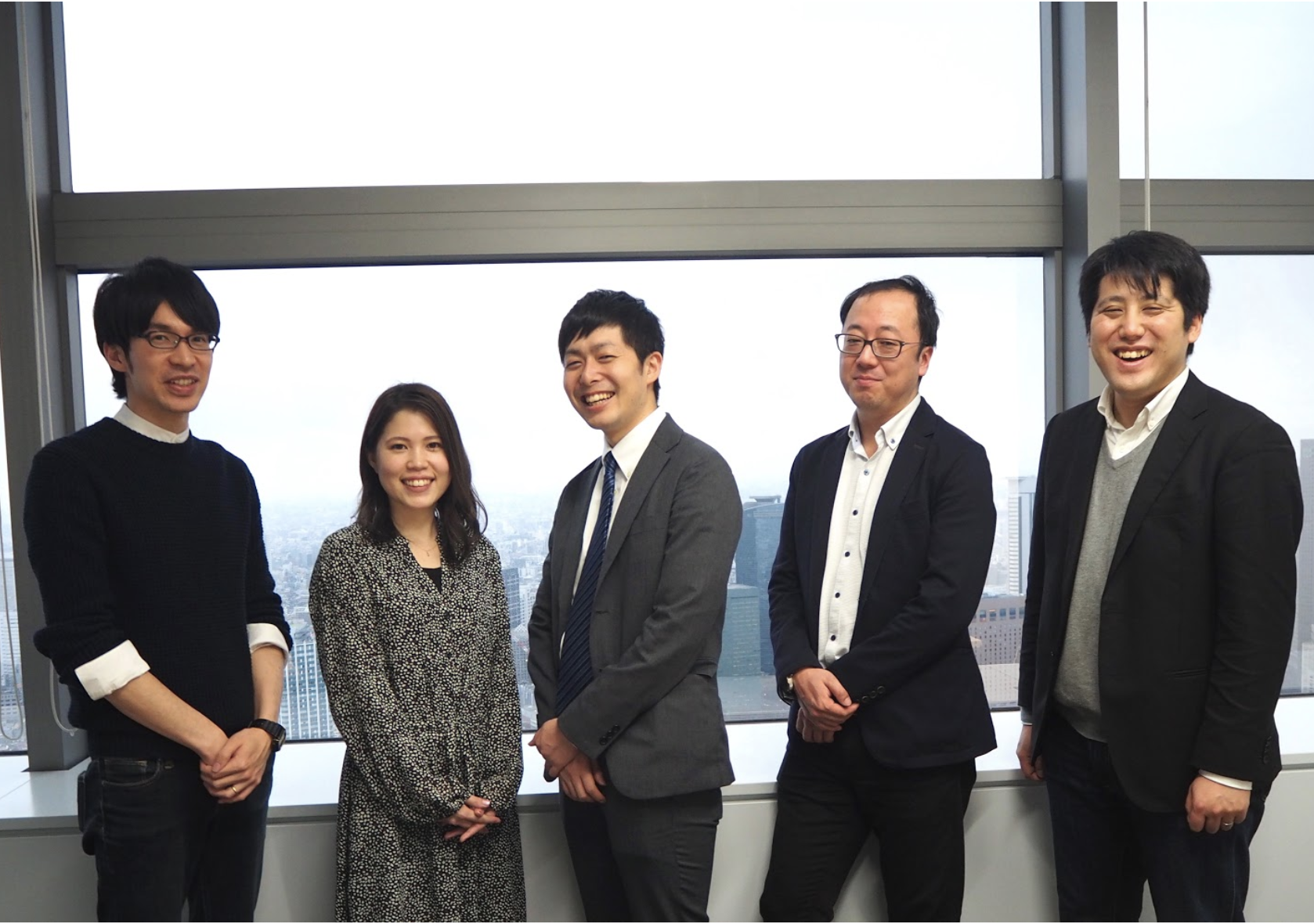
健診結果記録と健康管理機能がひとつになった一般ユーザー向けアプリ「CARADA」と健診機関向けの管理ツールをパッケージにした「健診機関向け CARADAパック」を手がけられているエムティーアイのCARADA事業部様。急成長するチームが次に行った一手について、CARADA事業部の「KCPチーム」のメンバーにお話を伺うことにしました。
■お話を伺った方
・高崎様(エムティーアイ CARADA事業部 グループリーダー)
・嶋様(エムティーアイ CARADA事業部 企画メンバー)
・上杉様(エムティーアイ CARADA事業部 企画メンバー)
・水上様(エムティーアイ CARADA事業部 企画メンバー)
・川瀬(ギルドワークス)
※このインタビューは2018年3月時点の内容で、役職もその時点のものです。
リーンキャンバス特訓で掴んだサービス企画のコツ
——高崎さん率いるKCPチームは、どのようなチームなのでしょうか?
嶋様(以下敬称略):弊社では、以前から『CARADA』という、健康診断の結果をスマホでチェックできる個人向けのアプリを提供していました。このアプリを健診機関と受診者をつなぐためのツールとして活かせるのではないかという問いかけから、我々はサービスを企画して立ち上げるチームとして出発しました。
上杉様(以下敬称略):受診者と健診機関の接点は、一般的に年1回の健診のタイミングしかありません。我々が提供する『健診機関向け CARADAパック』を活用することで「受診者との密なコミュニケーション」を実現し、受診者のリピーターの定着、受診後のアフターフォローの充実、他健診機関との差別化などをご支援していくことができます。
嶋様:サービスは2017年9月にリリースをしました。現在のチームでは、健診機関への導入のお手伝いと、健診機関の管理者や、個人の利用者がより便利に使えるような施策を行っているところです。
——ギルドワークスに相談された経緯を教えてください。
高崎様(以下敬称略):最初に相談したのは、2017年4月のことでした。私はもともと人事部だったので、サービス企画に携わるのは初めてでした。突然、短期間でそのコツを習得して、事業計画も立てなければいけないという立場に立たされてたのです。それで、「リーンキャンバスを1日で覚えたいから特訓してほしい」と川瀬さんにお願いしたのが始まりでした。
その時に川瀬さんと二人で課題を整理していくことで、自分たちの方向性も見えてきて。それで、川瀬さんにはもっと入り込んでもらおうということになったんです。

川瀬:リーンキャンバスの特訓は、お役に立ちましたか?
高崎:感謝しています。事業の立ち上げは、スピード感が求められる中、状況も刻々と変わっていきます。柔軟性も必要だし、その日に言われて次の日にはアウトプットしなければいけないという状況だったので、川瀬さんのアドバイスはとても役に立ちました。
川瀬:それは、よかったです。具体的にはどんな話が参考になりましたか?
高崎:環境が変わっていく中で利用者は常に変化していくということ。自分たちがターゲットだと考えているクライアントの課題にどういったソリューションをあてていけば効果的かという話が、かなり役立ちました。
—— 2017年9月にサービスをリリースされたとのことですが、感触はいかがでしたか?
高崎:健診機関にはこんな課題があって、こういった価値を求めらられるではないかということが、リーンキャンバスで整理したものから大きくずれることはなく、感触はとてもよかったですね。今でも、その感触は続いています。
チームでもっと上を目指すための「合宿」
——その後、合宿を行うまでにはどんな経緯があったのでしょうか?
高崎:最初に嶋くんと二人だけだったチームメンバーが、2017年の夏に水上さんが、秋に上杉くんが参加して、倍になりました。それまでは嶋くんとだけコミュニケーションを取っていればよかったのですが、4人全員が同じ方向を向いて仕事をしていくことが必要になりました。
嶋:さらに、高崎さんの中では次のステップも考えていたんですよね。
高崎:はい。今のサービスがある程度成長した時に、次にどう展開していくのかをそろそろ考えていかなければいけないと考えていました。なので、そういったことを話し合うための場を設けたいと思い、合宿を行うことにしました。
川瀬:キャンバスに描いた一つ目の山はすでに登れそうだったので、もう一つ二つ高い山を目指したいということでしたよね。
嶋:そうなんです。当初思い描いた目標は達成できそうだとわかってきました。そこで、自分たちは満足できるのかな?と思いました。思い描いているものよりも、まだまだ上があるんじゃないか。もっと、世の中に面白い提案ができるんじゃないかと。
高崎:要するに、現在のサービスを単に日本全国に広げるだけでは、自分たちは面白くなさそうだなというのが、私と嶋くんの共通の思いでした。
嶋:具体的には、受診者にとってこれまでになかった価値を生み出したり、健診機関の新たな売り上げにつなげたり、というサービスにすることが、僕たちKCPチームならならできるんではないかと思ったんです。
高崎:さらに、周囲の期待や、自分たちの今後のキャリアを考えた時に、「今年は勝負の年にしたいよね」という二人の思いもありました。そのためにはこれまでと同じことをやっていたらダメで、何か新しいことをしなければと思ったんです。
川瀬:なるほど。合宿をやると決めてからの高崎さんの決断は迅速でしたよね。そもそもなぜそんなにすぐに決断できたのでしょう?
高崎:嶋くんと、まだまだもっとよくできるという話をしている中で、「合宿やりたいよね」という話で盛り上がってしまって(笑)
川瀬:覚えていますよ!来週やりましょうぐらいの勢いがありました(笑)
自分たちの価値観を掘り下げて事業を自分事にする
川瀬:エムティーアイ社から合宿の依頼を受けるときは、サービスを設計しましょうとか、プロダクトを今すぐつくるための話になることが多いです。しかし、KCPチームは自分たちの価値観などを知るところから始められました。もちろん、私が提案したということもありますが、それに同調していただきましたよね。なぜそういうプロセスを受け入れられたのでしょうか?
高崎:多分、嶋くんの場合は「ただプロダクトを作る」という作業はお腹いっぱいだったと思うんです(笑)
嶋:そうですね(苦笑)今までにいろいろなサービスの企画に関わってきたのですが、言われたことだけをただ形に落としていくプロジェクトでは、そのサービスに愛着を感じられないこともありました。反対に、愛着を感じられたとしても、苦しんだりしていました。戦略という土台がしっかりしていないとある程度のところで伸びなくなってしまうんです。
高崎:誰かに押しつけられた仕事ではなくて、自分事にしたいという思いがあったのかもしれません。
—— 合宿をやると聞いた時、上杉さんと水上さんは率直にどう感じられましたか?
上杉:ヘルスケアの領域でサービス企画をしていきたいと考えていた僕にとって、もっと価値あるものを届けようという動きにつながる合宿への流れはとても嬉しかったですし、ワクワクしたのを覚えています。
水上様(以下敬称略):私の場合、最初に二人から話を聞いた時ははっきり言って、何をやるのかよくわかっていませんでした。でも初めての経験だったし、参加させてもらうことがまずはありがたかったです。
高崎:もともと水上さんには、企画業務のサポート的な役割としてチームに参加してもらっていたので、企画を立案するところには本来関わらないはずでした。でも、チームを一から作っていく、新しい企画を立案していくとなった時には、彼女のように前のめりで、勢いのある人と一緒にチーム作りを進めていきたくて加わっていただきました。
川瀬:合宿前には「健康とは?」とか「健康診断とは?」など、みなさんが深掘りしたいことについて話していきましたが、嶋さんに、上杉さん、水上さんは、それぞれ、大活躍されていましたね。
高崎:はい。自分たちのバックボーンの話から始まって、「健康診断というものが社会的にはこんな位置付けだけど、こういった位置づけに持っていきたいよね」というような話をしました。自分たちの中にある価値観からテーマを掘り下げていき、理想とする未来について語るといった流れでした。合宿前の事前ワークショップから、多くの時間を割いたように記憶しています。
「健康」に対するお互いの価値観を共有してみたら…?
——事前ワークショップを進めていく中で、みなさんの中に変化はありましたか?
上杉:健診の結果というデータを使って何かをしたい、人を健康にしたい、想いはあったのですが、「健康とは何か?」という問いに対して、改めて考えられたのがよかったです。普段から健康とはどういう状態なのかを考えてはいましたが、しっかりと「健康」について語り合う機会は貴重でした。
高崎:ヘルスケアのサービスに関わっていながら、あれほどじっくりみんなで健康について話し合うことはなかったよね。
上杉:はい。印象的だったのは、東洋医学の話になって「健康は輝きである」という意見が出たことですね。ぼんやりと考えていたところを、みんながそうだよねと言って、バックボーンから話していくと、確かにそうだなというところに落ちた。
健康の定義は、WHOや国をはじめ様々な機関が出しているけれども、『CARADA』としては、単に何かの指標に合わせるだけが健康ではないなと気付きました。『CARADA』を使う人が幸せになるような、気が充実するような状態にしたい、という方向性にまとまったのは大きかったですね。

——チームの気持ちや方向性が一つにまとまっていったという感じでしょうか?
高崎:そうですね。みんなの目指す方向性が、一つにまとまっていった感じはあります。じっくり話す時間をとると、お互いの価値観や方向性の違いが見えてくる。それぞれ年齢も性別も違うし、抱えているバックボーンの違いもある。合宿の前に前提として、その部分をしっかりと話し合って、お互いが把握できたことが、今考えるとやっぱりよかったなと思います。
お互いの価値観の違いを知ることで得られる2つのメリット
川瀬:合宿が始まる前に、深い対話を重ねることで「思考が移植されている状態」を目指そうということを提案しました。高崎さんがおっしゃるところは、互いの価値観の部分まで掘り下げて話をすることができたというところがポイントでした。
高崎:そうでしたね。個人的に合宿に期待することはいろいろありましたが、今後チームで気持ちよく仕事をしていくためには、ここで一度全部思っていることや価値観の違いを吐き出すべきではないかと考えていました。お互いが中途半端な解釈で仕事をしていると、結局それが仕事にも影響しそうだなと思ったんです。
川瀬:価値観の違いを共有することのメリットを、高崎さんはどうお考えですか?
高崎:まず、チームビルディングの観点からいくと、どんな仕事にアサインしてもらえばいいのかや、どういう達成感を味わってもらえばいいのかが見えてきました。苦手な仕事の時であっても、どうやってモチベーションを維持していけばいいのかということが分かるという点でもメリットがありますね。
嶋:今後、「新しいプロジェクトをスタートします」というようなことを言った時にもメリットがありますよね。僕たちの4人のように時間をかけてお互いの価値観を知って、それを既に共有できていると“これは何のためにやるのか”という根本的なところを改めて説明しなくていいので、その部分をすっ飛ばして仕事にかかることもできます。
——サービスの方向性を決めていくという点では、何かメリットを感じられましたか?
高崎:事前ワークショップの段階で、すでに価値観から方向性が見えそうな感じがしていましたね。
川瀬:互いの意見に同意させるのではなく、価値観まで垣間見えるような深い対話をすると「意味」が見えてくるんですよね。
高崎:事前準備の段階でそれぞれの価値観をもとに話していたことで、合宿では方向性が見えてきた。
川瀬:お互い根底から知るという行為に時間をかけると、初速は遅く見えますよね。でも、その後のアウトプットのスピード感や質の部分には違いがでていました。
——自分の思いを吐き出すことや価値観についてじっくりと話し合ったとのことですが、水上さんは振り返ってみてどう思われますか?
水上:合宿までは健康についてきちんと考えたことがなかったし、健康診断も自分が健康かどうか知るために受けるというよりも、会社から指示されて受けるものというイメージしかありませんでした。なので、健康について自分がどう考えていたのかを改めて考えさせられましたね。

高崎:水上さんの意見は、新鮮でしたね。それまでの流れを変えたというか。
水上:じっくりと話し合ったことで、このメンバーになら自分をさらけ出して意見を言うことができるようになりました。たとえ、私が的外れなことを言ってしまったとしても、まずは「そうだよね」と受け入れてもらえる。事前ワークショップではどこまで言ったらいいんだろう、何が正解なんだろうという思いがあったんですが、川瀬さんに「本音で話し合おう」と言ってもらったおかげで、徐々に本音を言えるようになっていきました。
川瀬:次第に水上さんらしさが出ていきましたよね。合宿当日の朝は、全員いお題を求めたのですが、その時には、とても積極的な水上さんに変わっていらっしゃいました。
——実際に合宿では、どのようなお題から話し合われたんですか?
嶋:たくさんの問いが出てきた中で、「医療従事者と健診結果でできることは?」と「実りある人生とは?」という二つのお題に絞って話し合いました。
川瀬:そうでしたね。その二つの問いから生まれたお話は、そのまま一つのサービスに落とし込めそうなレベルの深い話し合いに発展していました。みなさん、かなり本音で話されていたという実感があります。
嶋:本音で話せていたのは、このチームでならこんなことも、あんなことも話し合えそうだという信頼が生まれたからかもしれません。どんな質問や問いであってもみんなに問うことができる環境が、事前ワークショップを通じて既に合宿の前にできていた。社会人だからとか、会社員だからとかいう立場ではなくて、自分のバックボーンを含めて素の自分に立ち返って健康について話し合えたことで、前提ができたという感じがしました。
川瀬:信頼を醸成していくことは、チームをビルディングするということ、サービスの方向性を探索していくということ、これら2つの行為に大きく影響していることが、皆さんも実感できたのではないかと思います。
議事録を捨て、グラフィックレコーディングしてみた
——ほかにも、価値観を掘り下げていくという過程を深めるために、ファシリテーターは何か工夫をされたのでしょうか?
川瀬:さまざまな工夫を施していますが、今回の合宿での新しい工夫としては、話し合ったことをグラフィックレコーディング(グラレコ)というかたちで絵や図に記録を残していったことでした。
高崎:通常であれば、一般的ないわゆる議事録というものでもよかったのかもしれません。でも、議事録だと自分がどういう思考でその発言をしたのかや、どうしてその疑問を深掘ろうと思ったのか、思考のプロセスみたいなものが表現されない。その点グラレコは後から見返して、みんなとの会話の流れを思い出すためには分かりやすい手法だったなと思います。後、グラレコで記録したものを見ると、話し合えていない部分も見えてきましたね。
嶋:重要なワードとかは覚えているんだけど、時間軸の中では「点」でしか記憶は残っていないから、それがどのような文脈で発せられた意見なのかは覚えていない。でも、今回はグラレコのおかげで、その文脈を共有することができたし、スピード感を上げるために大きく役立ったような気がします。
水上:そうですね。事前ワークショップが終わった後に見返すと、今日はここまでしか話せなかったけど、もっと話を広げられそうだなとか、意見をもっと言えそうだなとか、考えがどんどん出てくるようになりました。
川瀬:合宿で話し合いたいお題を募集したときには、膨大な量の問いがみなさんから出てきて驚きましたが、お役に立っていたようでよかったです。
「これって、輝けるの?」 〜 合宿後に起こった変化
——この合宿で得たものや、みなさんの中で何か変化はありましたか?
高崎:チームビルディングについては、だいたいイメージしていた状態にまでなれたなという感じがしますね。サービスの企画をしていく上でも、大事なことをチーム全体が共有できたので、もしもこの先何か起こったとしても拠り所みたいなものができたというか。
川瀬さんに最初に相談した当時は、この先のサービスを考えたくてもまだ不透明な状態でした。この先々を見通したときに、このサービスはどうなっていくんだろうか、チームは存続していけるのだろうかといった一種の閉塞感みたいなものがあったので、一体感が生まれたことは本当によかった。
川瀬:合宿後、チームの熱量がすごくて、同じ部署内の別のチームであるCCPチーム(事例にリンクを貼る)の方が「KCPチームが羨ましい、僕たちも合宿をやりたい」とおっしゃってくださいました。事業部全体に火をつけていくという副次的な効果も出てました。
上杉:僕は合宿を終えた直後は、みんなで目指す方向性が見えたことが大きかったなと思っていました。でも、今考えてみると「健康とは輝きである」という根本のところをみんなで認識できたのがやっぱりよかったし、ヘルスケアのサービスをやるということはこういうことだよな、ということを再認識できたこともよかったですね。
川瀬:なるほどですね。
上杉:それから、僕は業務内容的にエンドユーザーの近くに行くことが多いのですが、その時の気持ちも変わりました。まだまだ変わる余地はあるとは思いますが、『CARADA』のユーザーが輝くことを想像しながら仕事をできるようになってきたのは大きな変化だと思います。
川瀬:それは深いですね。上杉さんは合宿を始める前、ヘルスケア領域で何かやりたいという思いはあったけど、具体的な姿がまだ見えないということを個人的な課題にされていましたよね。
上杉:はい、以前は「何か大きいことをやりたい」くらいのアバウトな思いしかなかったです(笑)。でも、誰かが喜ぶサービスにしないと意味がない。僕たちの場合は「エンドユーザーさんが輝く瞬間をつくる。」ことなんだなと再認識できました。
嶋:僕もあの合宿を機に、もっといろんなことをやっていいんだという気持ちになれました。健康というものをそれまでは小さく考えていたけど、枠にとらわれない広い考えで見てもいいんだなと。それから、業務的にハードな時期を乗り越えたらまた楽しいことができるんだという、モチベーションを保つ指針にもなった気がします。
あとは、何をする時でも「これって、輝けるの?」と考えるようになりましたね。シンプルな問いなんだけど、これってすごく強い問いだなと。

水上:私の場合は仕事もそうですけど、仕事以外の時に特に「これって、輝けるの?」ということを考えるようになりました。自宅から駅まで自転車で通っていたのを、最近歩きに変えたんです。自転車が健康でないということではないですが、歩きにしたら新しい発見をたくさんするようになって、それが自分の輝きにもつながっているなと思うようになって。その毎日の発見や驚きが、サービス企画の原動力にも通じています。
川瀬:水上さんは、合宿を終えてからもサービス案をどんどん出されていますよね。そして、その案の内容は、合宿の時に見つけた方向性から全然ぶれていない。素晴らしいと思います。
嶋:合宿後の変化といえば、たまにチームみんなで外にご飯を食べに行くようにもなりました。そこでは、よく健康について話します。それ以外でも、日々話せる状態になってきていますね。
——みなさんのお話を聞いてきた上で、KCPチームを率いる高崎さんは改めてどう思われますか?
高崎:合宿を終えて今、自分たちが考えている理想とアウトプットがかけ離れているということは、ほとんどなくなったように感じています。
川瀬:すごい変化ですね。
高崎:僕から見ればですが。でも、見当違いなことをやっているということは、ほぼなくなりましたね。きめ細かな指示を出さなくても、メンバーが自律的に動けているので、より高いレベルに向けて仕事をすることができています。投資対効果もあるといって、いいのではないでしょうか。
——最後に、今回の合宿はKCPチームにとって何だったかを教えてください。
高崎:チームビルディングという観点では「土台作りができた」、サービス企画の観点では、「芯が通った」という表現がしっくりしそうです。今回の合宿で得たものを温めていって、今後も定期的に合宿をしたいですね。その時には、またご相談させてください。
川瀬:はい!ぜひ、やりましょう!
こんなことでお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。ギルドワークスのメンバーがお話をお聞きします。
- 立ちあげたい事業があるが、本当に価値があるのかどうか自分で確信が持てない
- 新規事業を立ち上げなければならなくなったが、潤沢な予算があるわけでもないのでどうしたらよいのかわからない
- 企画が実現可能かどうか開発の視点を組み入れながら仮説検証したい
- はじめてのことばかりで右も左もわからない
