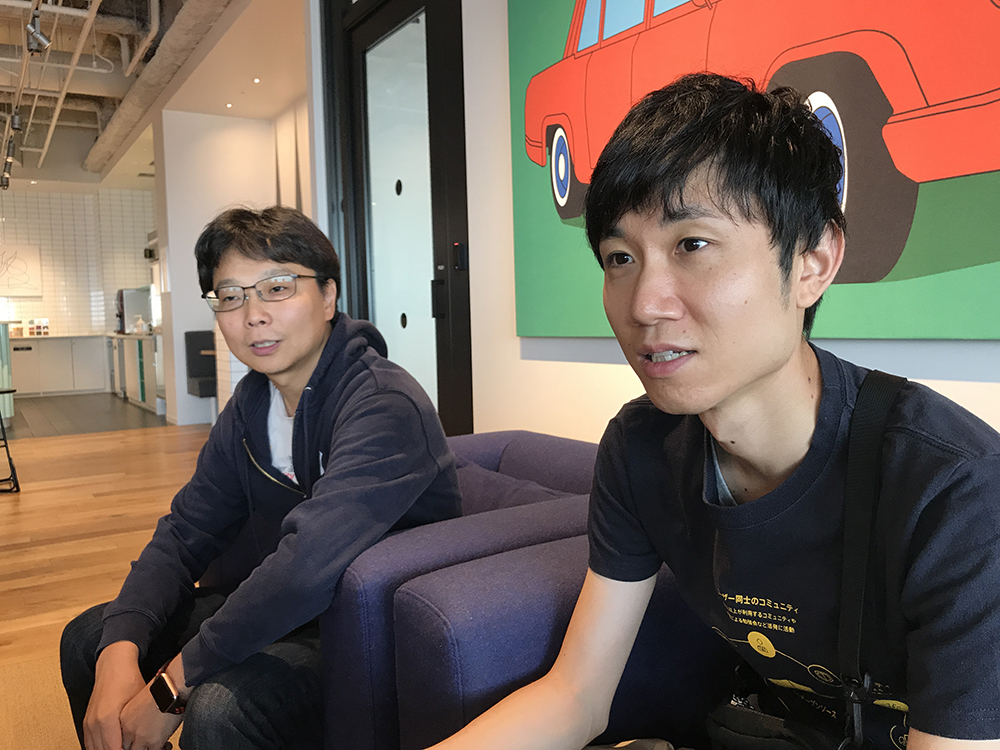- #開発現場コーチング
株式会社イーシーキューブ
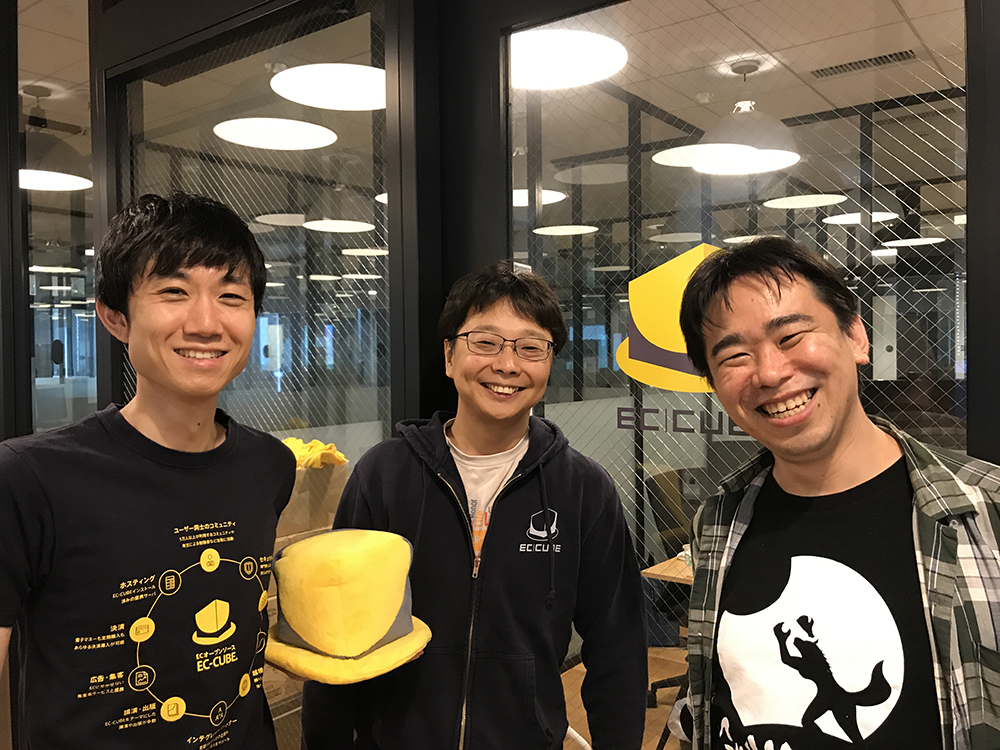
オープンソースのEC向けコンテンツ管理システム『EC-CUBE』の開発などを手掛ける株式会社イーシーキューブ様。開発チームはEC-CUBE本体の開発をはじめ、プラグイン提供・販売サイト『オーナーズストア』の運営やプラグインの審査なども行っています。
そうした幅広い役割を持つ開発チームがアジャイル開発に取り組み始めたものの、なかなか当初想定した成長を実現できていませんでした。そこで、以前からお付き合いがあった現場コーチの中村が、短期集中型でサポートすることに。スクラムマスターやメンバーは、スクラムに対する考え方やアクションがどのように変化したのでしょうか。
スクラムマスターの遠藤様、社長の金様にお話をうかがいました。
(肩書き、状況などは2019年8月2日当時のものです)
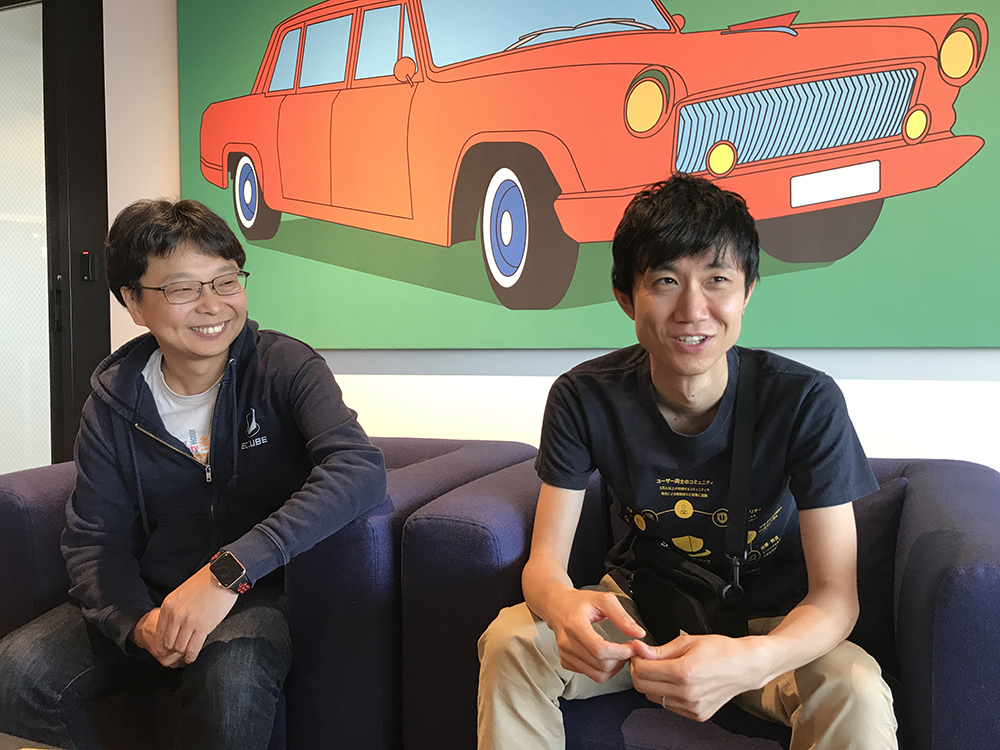
「もう今のタイミングしかない!」と決断
ーー現場コーチ加入前はどんな課題を感じていましたか。
遠藤:チーム体制が変わり、私が明確にスクラムマスターになった2019年4月から、中村さんには現場コーチとして週1回来ていただくことになりました。それ以前から私個人に対してアドバイスをしてくださる形で関わってもらっていました。中村さんのアドバイスを私が現場に伝えるというリモートコーチングみたいな形でしたが、なかなか細かい部分まで伝えきれず、その結果開発ペースが安定しなかったり課題も少なくなかったです。
もちろん、いったん立ち止まってチームの将来や取り組み方について話し合う時間が必要だと理解してはいたのですが、なかなか共感を呼ぶような伝え方ができずに悩んでいました。
そこで、もう自分がハブとなって現場に伝えるよりも、中村さんに現場コーチとして開発現場に来てもらって、その場で直接伝えてもらうのが良いと考えたんです。
中村:4月以前は、私自身が遠藤さんの振る舞いを見ていない中、どう伝わっているのかが見えなかったので難しかったですね。社内やチームの中に、遠藤さん以外にもう1人ぐらいスクラムに前向きな人がいれば良かったんですが、最初はあまりいなかった。
金さんは経営者として「任せる」という姿勢を貫いていましたし。
金:アジャイル開発って、上から押しつけられて取り組むものではありませんからね。私は以前から、中村さんに短期集中型で参画してほしいと思っていました。
でも、私が「中村さんに来てもらえ」と言うのは意味がないでしょう。私としては、遠藤に自身の経験や知識を高めてほしいという期待がありましたから。また、遠藤の相談相手は、僕以外にもいた方がいい、とも思っていました。
中村:あと、遠藤さんを含めたスクラムメンバー全員が、チーム立ち上げはもちろんアジャイル開発に取り組むのが初めてというのも影響したかもしれませんね。
遠藤:ただでさえ日々の仕事に追われオーバー気味の中で、まったく新しいことに取り組もうとすると絶対オーバーフローしてしまう。
ならば、今やっているスクラムのイベント内で直接フィードバックをもらえば、メンバーの負担も最小限で済むので受け入れてもらいやすいんじゃないかと。そこで、水曜にやっていたスクラムイベントを木曜にずらして、中村さんには現場コーチとしてスクラムイベントの場に来てもらおうと考えたんです。
ーー現場コーチにはどんな期待をしていましたか。
遠藤:まだスクラムに懐疑的なメンバーに対して背景や目的といった観点からうまく伝えてもらったり、僕自身が違う方向に行きかけた時に外の視点から補正してくれたり、正しいフィードバックをもらいたいと思っていました。
当時って、スプリントは回っているし成果物も出ていたんですよ。ただ、開発ペースも安定しないし、思ったほどの成果が得られていなかった。
中村:私の最初の印象は、何かスプリントらしきものは回っているが、自分たちがそれを何のためにやっているか分からないまま、遠藤さんに振り分けられたから取り組んでいるという感じに見えました。参画当初は「何のためにやっているの?」と聞いたら「わかりません」って答えが返ってきた(笑)。
遠藤:確かに、イベントはこなしているが、意味や効果は理解していない感じだったかも。
中村:最初の頃は「もっと良くしていこう!」という意欲があまり感じられなかったですよね。
遠藤:スクラムで開発の透明性が上がると、成果以上に自分たちの実力不足というか、できていない部分も明確になってくるじゃないですか。その現実にモチベーションが下がったり、現実から目を背けようとしそうな時期だったのかもしれません。
ーー現場コーチ導入で思うところはありましたか。
遠藤:ふりかえりの時にもらう客観的な視点からのフィードバックは、メンバーに多くの気づきややる気を与えてくれると思っていました。スクラムマスターの役割のひと1つである「メンバーに対するティーチングやコーチング」に関する部分は、誰かにサポートしてほしいという気持ちがあって。
そういう意味で、私自身は中村さんが後ろで見守ってくれるという安心感とプレッシャーの両方を感じていました(笑)
中村:スクラムマスターの役割にふさわしい振る舞いかどうかを質問するようになったので、プレッシャーだったと思います(笑)
金:でも、現場コーチに週1回来てもらうと決めた時、遠藤の成長を感じました。先述の通り、それまで水曜がスクラムイベントの日だったのですが、木曜にずらしたいという話を持ってきたんですよ。
その時、「スクラムマスターとしてチームを成長させていく上で、中村さんにも直接来てもらうことが必要。そのためにスクラムマスターの責任で木曜日にさせてくれ」と言ってきたんですよ。たぶん昔の遠藤なら、私が過去に決めた水曜日を木曜日に変更したいと言わなかったと思います。その瞬間、「おお!ついに一歩踏み出したな!」と思いました。しかも、相談じゃなくオーダーとして持ってきましたから。
遠藤:あの時は、成果を出せるスクラムに変えるなら、もう今しかないと思っていました。かなり危機感があって、自分も変わらないといけない想いがありましたから。

縛りを外して「もっと実験してもいい」という気づき
ーー現場コーチが参画したことで、どんなメリットや新たな気づきがありましたか。
遠藤:ひとつはふりかえりやスプリントレビューの後に、中村さんからフィードバックをもらう時間を設定しました。その結果、その場で「次はこれにトライしてみよう」と、その場で次のアクションまで決まるシーンが増えたんです。
「筋の良い問いかけ方をすれば、しっかり考えてくれる」という気づきは大きかったし、勉強になりました。
中村:遠藤さんは「何かありませんか?」という問いかけをしていたんです。ある時「結果の数字は見ていますか?」とメンバーに問いかけたら「いや、見ていません」という答えが返ってきた。「それはOutputでしかないので、Outcomeをちゃんと見よう」と伝えました。
さらに続けて「数字は全員が見られるの?」と問いかけると、「見られません。他のチームの人達が見れます」という答えが返ってきた。「それはチームの役割を狭くしているよね。全員が見られるようにするにはどうすればいいか」という話に進んでいきました。
問いかけは、会話が生まれるきっかけにならないといけないんです。
金:中村さんとは付き合いが長いこともあり、私にも忌憚ない意見をくれたのは助かりました。
中村:金さんは役職とEC-CUBEへの想い、両方ともメンバーの誰よりも強い。しかし、チームはそこまでの想いを醸成できていないので、どうしても金さんと議論しても勝てないというどこか諦めに似た、あるいは対等でないといった意識が生じてしまう。
誰も金さんに「それは違うんじゃないですか」とは言えないでしょうから。そこを第三者的な私が意見することは、役割のひとつでもありました。なるべく思ったことは素直に言うようにしていましたね。
金:メンバー全員、素直過ぎるぐらい素直なんですよ。私が言った言葉を消化できていなくても「そうなんだ」と受け入れてしまう。中村さんの意見をきっかけに、「私も別の考えがあるんじゃないかと思ってた!」という気持ちに気づけたメンバーもいたと思いますよ。
遠藤:チームにとっては、見えない枠に囚われていることを指摘し、枠を外してくれる存在ですね。「今までこういうやり方だった」とか「誰かじゃないとレビューできない」とか「絶対に問題解消できる方法じゃないと、アクションしてはいけない」などと、勝手な縛りを決めていた。
もっと実験して良いという気づきが1番大きかったかも。そんな“枠を外す”ようなフィードバックを沢山もらえました。
中村:あとはスクラムが初めてのメンバーばかりだったので、「他の現場ではこんな時、こうやっていたよ」という情報提供も積極的にするようにしていました。
ーー実際に取り組んでみて、本で読んでいた頃のアジャイル開発に対する考え方が変わりましたか。
遠藤:ようやくしっかりとスプリントが回るようになってきたと思います。
中村:始めた頃よりも確実に成長して、安定した成果を出せるようになっていると思います。
ただ、難しい開発の部分はチームではなくCTO個人が解決していたり、ユーザーインパクトが高い成果を出せていない現状が見えてきて、自分たちのスキル不足を感じ始めている時期なんだと思います。
金:チーム内に存在する課題の質が変化してきたでしょう。最近は自分たちで考えてアクションしたり、自分たちで情報を集めに行く動きをした結果、自分たちのスキル不足で失敗する経験を何回かしているから自信を失いかけているけど、昔はこんな「良い失敗」はしていなかったから。
遠藤:確かに、以前は言われたことを言われた通りにこなすだけでしたね。今は、いろいろ新しいことにもチャレンジしてみようという雰囲気も出てきましたし。モブプロにも挑戦するなど、視野は広がってきたのかなと。
現場コーチのサポートによって、課題の質が変化してきた開発チーム。
後編では、現場コーチの登場により得られた気づきや、経営者の立場から見た現場コーチの効果などについて語っていただいています。
こんなことでお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。ギルドワークスのメンバーがお話をお聞きします。
- 立ちあげたい事業があるが、本当に価値があるのかどうか自分で確信が持てない
- 新規事業を立ち上げなければならなくなったが、潤沢な予算があるわけでもないのでどうしたらよいのかわからない
- 企画が実現可能かどうか開発の視点を組み入れながら仮説検証したい
- はじめてのことばかりで右も左もわからない